公開日:2016年07月06日
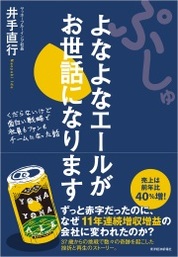 『ぷしゅ よなよなエールがお世話になります』井手 直行/著 東洋経済新報社
『ぷしゅ よなよなエールがお世話になります』井手 直行/著 東洋経済新報社
ビールがおいしい季節です。
売り場に並んだ数々の缶ビールの中で、変わったネーミングと変わったデザインのビールに目を引かれたことはありませんか。そのビールは、この本に登場する「知的な変わり者」集団が作ったビールかもしれません。
1990年代後半の地ビールバブル崩壊後にどん底を味わったこのクラフトビール会社は、その後、業績をV字回復させ、11年連続増収増益を果たします。現在の代表取締役である著者がそのために行ったのは、「チームづくり」でした。
この会社の営業担当として旗揚げから携わってきた著者は、会社の危機に際し、まずは単なる傍観者となっていた自分の意識を変え、スキルを磨き、社員をチームにし、「ビールに味を!人生に幸せを!」というミッションを共有し、チーム力で周りにそのビジョンを伝え、さらには販売店や顧客までをもチームにしてしまいます。
本人が変わることで、周りがどんどん変化していく様子は、その手法が日々の仕事の参考となるだけでなく、読んでいて、とても爽快で楽しい気分になれます。
こだわりのビールを楽しむようにこの本を読んでみませんか。
公開日:2016年06月15日
 『先生、NPOって儲かりますか?-若者たちが地元で賢く生きる方法』渡辺 豊博/著 春風社
『先生、NPOって儲かりますか?-若者たちが地元で賢く生きる方法』渡辺 豊博/著 春風社
著者は35年間静岡県庁に勤務した後、都留文科大学教授として活躍するかたわら、これまでにまちづくりなどの9つの事務局長を務めた経歴の持ち主です。
この本では、三島市のNPO法人「グラウンドワーク三島」の専務理事・事務局長の立場で、23年間の市民主導の環境改善活動の経験をもとに、地域の活性化に結びつけるNPOビジネスのノウハウや経営戦略を紹介しています。
1992年に設立当時から中心となって関わった「グラウンドワーク三島」は、「水の都」三島市において、1964年以降地下水が減少して地域の川が汚れ、ふるさとが駄目になってしまうという危機感をもった人たちが、もう一度ふるさとの水辺の自然環境を再生・復活させることを目標にして、立ち上げました。現在では「水の都」を彷彿させる清流となり、市内中心部を流れる源兵衛川ではゲンジボタルをよみがえらせるといった成果を上げ、まちづくりの実績が社会的に高く評価され、2005年度都市景観大賞「美しいまちなみ大賞」をはじめ様々な賞を受賞しています。
こうした活動を継続するためには、補助金や助成金に頼るだけではなく、NPO自らが利益を生み出す経済的仕組みをつくることが重要であると解説しています。「グラウンドワーク三島」では、地域の60歳以上のおばちゃんおじちゃんを雇用して、「三島街中カフェ」を三店経営し、この「NPOビジネス」を収益事業と位置付け、活動の基盤としています。
地域の「資源」を見つけ、「地域に根付いた、生活者の要望に沿った、地についた商売や小さな産業の創業」を目指すことや、NPO活動には常にリスクへの備えが必要であり、「事故の危険性を事前に告知したことを証明できなければ、損害賠償の責任を負う」など、著者の現場の経験に基づくNPOビジネスのノウハウとして、重要なアドバイスが詰め込まれています。
最後に、著者が2015年富士宮市にある県立富岳館高校で行った「出前授業」の講義内容を文章化し、「人生、迷い、考え、悩んでばかりはいられない」「現場には人の生き方を学ぶ知恵がある」等、若者たちへ熱いメッセージを送っています。そのメッセージはNPO法人の責任者として長い間担ってきた現場の経験から積み上げられた想いがちりばめられています。地方に隠れているビジネスチャンスをみつけて、地方の活性化を図るヒントになるかもしれません。
公開日:2016年05月17日
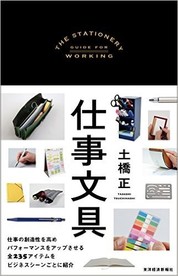 『仕事文具』土橋 正/著 東洋経済新報社
『仕事文具』土橋 正/著 東洋経済新報社
新年度や新しい環境で生活をスタートするとき、気分をちょっと変えたいときなど、筆記具やノートを新調すると「よし、やるぞ!」という気持ちになります。
この本は、新商品だけでなくロングセラー商品も含め、「仕事の創造性を高めパフォーマンスをアップさせる」著者選りすぐりの全235アイテムを、「情報をインプットする」「情報・書類を整理する」「技ありノート」「仕事がはかどる名刺管理ツール」「大人のペンケース」「ショップオリジナル文具で個性を出す」など22のコンテンツに分けて紹介したものです。
例えば、カバーをアーチ状にすることで使っている途中でちぎれにくくした消しゴム、引き終わりがきれいに切れる修正テープ、エッジが工夫されていて紙の切れ味抜群のアルミ定規、A4サイズの紙をずらしながら切るという煩わしさから解消される二つ折りカッターマットなど、その機能性を知るとぜひ使ってみたいと気になるものばかりです。また「スケジュール管理をスムーズにする手帳&アシストツール」で取り上げられたラベルシールについては、意外で効果的な使い方も紹介されています。
そして「万年筆のすすめ」では、その魅力や種類、購入時のポイントやメインテナンスなど、「鉛筆を使いこなす」では、魅力や書き味、種類などについて特に詳しく書かれており、どれが自分に合っているかを決める際の参考になりそうです。
著者は、ステーショナリーディレクター、文具コンサルタントとして文具の企画やコンサルティング、売り場のプロデュースなどを行っており、新聞・雑誌へのコラムのほか、『文具の流儀』(東京書籍 2011年)『やっぱり欲しい文房具』(技術評論社 2006年)など文具に関する本を多く執筆しています。
この本を参考にして、仕事のさまざまなシーンで便利に使えるお気に入りの文具を探してみませんか。
最後にもう一冊。小学生が夏休みの自由研究でまとめた『文房具図鑑 その文具のいい所から悪い所まで最強解説』(いろは出版 2016年)が注目されています。六年生の山本健太郎さんは、一年かけて文具を観察し、実際に使って比較分析して100ページの本に仕上げました。手描きのイラストは圧巻で、コメントにも説得力があります。こちらも併せてぜひ読んでみてください。
公開日:2016年04月15日
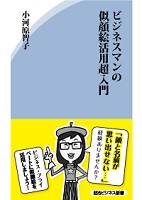 『ビジネスマンの似顔絵活用超入門』小河原 智子/著 経済法令研究会
『ビジネスマンの似顔絵活用超入門』小河原 智子/著 経済法令研究会
皆さんは人の顔を覚えるのが得意ですか?
ビジネスチャンスは人とのつながりで広がっていきます。二度目に会ったとき、相手の顔を覚えているかどうか、それでその後の付き合いが変わることもあるかもしれません。
この本は、似顔絵アーティストである著者が独自に考案した「ポジション式似顔絵法」で似顔絵を練習しながら、顔の識別能力を高め、その結果、人の顔を覚えることによって仕事や地域での活動がスムーズになるというお役立ちの一冊です。
「ポジション式似顔絵法」とは、まずは、モチーフを「大まか」に捉え、目鼻などのパーツの配置(=ポジション)の特徴を「上型」「下型」「平均型」「内型」「外型」の5つのパターンに振り分けるところから始まります。例示されている写真と図解で、ポジションに注意して描くだけで似ている似顔絵が描けるということがわかります。また、それぞれのパターンによって、顔から受ける印象は異なっており、「人の顔を覚えるための最大の意識」である「興味」を持つためにも、その人の最初の印象をきちんと感じておくことが必要であると著者は述べています。
ポジションを正しく識別した後は、パーツ仕上げです。輪郭の基本形や、髪型の見つけ方、黒目の面積の描き分け方などが、各パーツのバリエーションとともに、わかりやすく解説されています。
一般の方20名の顔写真を例題にした「ちょいメモ似顔絵にチャレンジ!」では、著者のアドバイスに従いながら、初見の方の特徴を捉え、似顔絵にする特訓を行います。20人の似顔絵が完成する頃には、十分な力が備わるのではないでしょうか。
また、似顔絵は、相手を描くだけでなく、名刺やチラシなどに、自分の似顔絵を使用することで、伝えたいことなどの方向性を写真とは比べものにならないほど表情豊かに描きこむことができ、印象に残るという効用もあると記されています。
出会いの4月です。
新しく出会った人の顔を覚えるために、そして自分のことを覚えてもらうために、似顔絵をコミュニケーションツールにしてみませんか?
公開日:2016年03月15日
 『好きなようにしてください-たった一つの「仕事」の原則』楠木 建/著 ダイヤモンド社
『好きなようにしてください-たった一つの「仕事」の原則』楠木 建/著 ダイヤモンド社
著者の楠木氏は、一橋大学大学院国際企業戦力研究科教授で、専攻は競争戦略です。
この本は、ソーシャル経済ニュースメディア「NewsPicks」での週一回の連載「楠木教授のキャリア相談」の一年間分をベースに加筆修正し、未収録の章を新たに加え書籍化したものです。年齢の若い読者が、仕事や仕事生活に関わる「迷い」や「悩み」を短い相談文にして編集部に送り、それに著者が答えるという形式で、50の事例が掲載されています。
その回答のほとんどに、楠木氏は「好きなようにしてください」と答えています。一見すごく投げやりな言葉のようですが、そのあとに楠木氏自身の仕事に対する考え方を伝え、時には厳しく、時にはユーモアに溢れた視点でアドバイスをおくっています。
たとえば「内定している大企業と、現在のアルバイト先で仕事が面白いと感じているスタートアップ企業のどちらに就職すべきか悩んでいます」という悩みには、それは「仕事」についてではなく実は「環境」について悩んでいて、本来は「仕事」の内実が判断基準になるべきだと述べています。世の中に実際にはそんな「最適な環境」は存在しないので、今自分が面白い仕事だと気に入っているスタートアップ企業で仕事をするべきだと回答しています。要するに「好きなことをする」に越したことはないということを伝えています。
また「井深大やジョブズのような『プロ経営者』に最短距離でなるためには、どんな企業や分野からビジネスマンの修行を始めるのがいいのでしょうか?」という悩みには、欲と夢は異なり、彼らはいい仕事をしてきたから成果を出してきたのであって愚問だと言っています。「仕事」は「趣味」とは違い「自分以外の誰かに対して大きな価値をつくったということ」、言い換えると「仕事は他人のためにやるもの」であり、まずは「仕事」について正しい認識を持つべきとしています。
また、「経営学という仕事」、「仕事の原則(僕のバージョン)」といったコラムがあり、主張のベースにある「自分がどういう仕事をして、日々の仕事に対してどういう構えをとっているか」についても述べています。
「仕事」とはいったい何なのか、「仕事」にどう向き合っていくのかということを、あらためて考えるきっかけとなる一冊です。
公開日:2016年02月16日
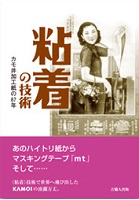 『粘着の技術 カモ井加工紙の87年』粘着」の技術 編集委員会/編 吉備人出版
『粘着の技術 カモ井加工紙の87年』粘着」の技術 編集委員会/編 吉備人出版
生きたハエがくっついて動けなくなる茶色い粘着質のテープ「ハイトリ紙」を知っていますか。これを作っているのが1923年(大正12年)創業の岡山県倉敷市に本社を置くカモ井加工紙株式会社です。
この本は、2010年(平成22年)に創業87周年を迎えた会社の歩みとモノづくりについて書かれています。History、People、PR&Adds、Technology、Challenge、Futureの6つのパートに分かれていて、写真も多く掲載されわかりやすく、興味がわいたところから読むことができます。
パート1History「すべてはハイトリ紙から始まった」では、1930年(昭和5年)の爆発的なヒット商品となった「カモ井のリボンハイトリ」の発売、戦時中の海外市場における日本商品ボイコット、戦後混乱期の危機からの脱出、製造拠点の海外移設によるコストダウン、建築や塗装の工業用マスキングテープの発売など、ハイトリ紙をめぐる会社の変遷を詳しく知ることができます。また、パート5Challenge 「マスキングテープの新たな挑戦」では2007年(平成19年)に誕生したマスキングテープ『mt』について書かれており、特に、東京のギャラリーカフェ店主からの一通のメールが、職人のマスキングテープから新たな雑貨のマスキングテープへと大きな転換のきっかけとなったという興味深いエピソードも紹介されています。
パート3PR&Adds「資料室から見えてくる遊び心の遺伝子」では、テレビCMや宣伝ポスターなどが会社の資料室に保管されており、その貴重な資料を見ることができます。パッケージやノベルティーグッズのデザインには「遊び心」が満載で、商品に対する意気込みが感じられます。
「粘着」の技術にこだわり続けるぶれない姿勢を貫きながら、常に「現場の声に耳を傾け、職人の細かな要望に応える」ことで苦境を乗り越えてきたカモ井加工紙。この本には、時代のニーズに柔軟に対応することで生き続ける中小企業の経営のヒントが多く込められています。
現在のヒット商品となったマスキングテープ『mt』は、「創造者の商品に対する愛情が、訳もなくさまざまな色彩のテープを買いたくなる衝動を呼び覚ましそうなチャーミングなデザイン」と高い評価を得て、2008年度(平成20年度)の日本全国のデザインを対象としたグッドデザイン賞を受賞しています。
中央図書館では、2016年(平成28年)2月18日(木)から3月27日(日)まで、企画展「第14回 ひろしまグッドデザイン賞」を開催します。広島市内の企業が製造・デザインした商品やパッケージの中から、特にデザインの優れた商品を表彰する「ひろしまグッドデザイン賞」の第14回受賞商品を展示・紹介します。あわせてこちらもご覧ください。
公開日:2016年01月15日
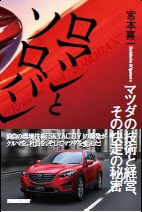 『ロマンとソロバン』宮本 喜一/著 プレジデント社
『ロマンとソロバン』宮本 喜一/著 プレジデント社
「君たちにロマンはあるか?」
「世界一のクルマをつくろう」
2005年7月、マツダは全組織を巻き込んだ長期戦略策定プロジェクトチームを発足させました。研究開発分野のチーム責任者となった常務執行役員の金井誠太氏は、引き受ける以上、自分の方針を貫きたいと考え、この計画策定活動を活用して、フォードの経営手法が導入されて以来、開発陣の頭にこびりついている制約を勘定に入れるというソロバンを取り払い、ロマンを共有することで、チーム全員の士気を上げ、斬新な発想を駆使できる環境を与えようと尽力します。
この本は、ハイブリッドカーや電気自動車などのエコカー開発に出遅れたマツダが2010年に独自の環境技術「SKYACTIV(スカイアクティブ)」を開発するまでの道のりを、それに関わった複数の人々の目線で記したルポルタージュです。
新開発の高圧縮エンジンの技術的課題を乗り越えていく過程は、技術者、開発者の息づかいがそのままに感じられます。
「世界一のクルマ」をつくるには、フォード流の「トップグループの一角を占めていれば合格」という発想から抜け出し、マツダの、マツダによる、マツダのための開発が必要でした。同時にフォード傘下でそれを実行するには、ソロバン感覚も忘れてはなりません。
社員の意識改革と、仕事をスムーズに行うための組織改革、小さなシェアのスモールプレーヤーの特徴を存分に活かした独自性の追求により、新技術は実現可能となりました。その後押し寄せる2008年のリーマンショックや2011年の東日本大震災などの困難な状況ににも負けず、成し遂げることができたのは、関わる全ての人がロマンとソロバンを共有し、そのためにマツダが何をすべきかという共通の認識の下、それぞれの役割を果たしたからでした。
現社長の小飼雅道氏は「会社は経営者が動かしているのではありません。ひとりひとりの挑戦する意欲、気持ちが会社を支えているのです」と言います。
日々の業務に追われてばかりだと思った時、是非この本を読んでみてください。チームで目標を定め、同じ方向に向かって、各自が何をすべきかを主体的に考えながら実行するという、仕事の基本に立ち返ることができると思います。
公開日:2015年12月15日
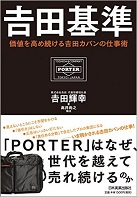 『吉田基準~価値を高め続ける吉田カバンの仕事術』吉田 輝幸/著 日本実業出版社
『吉田基準~価値を高め続ける吉田カバンの仕事術』吉田 輝幸/著 日本実業出版社
「吉田カバン」という会社名を聞かれたことがありますか?
「ポーター」という名のカバンの会社として知っている方や、機能性を重視したおしゃれなカバンをつくる会社としてすぐ思い浮かべる根強いファンの方も多いかもしれません。
吉田カバンの看板商品である「タンカー」というシリーズのカバンは、1983年(昭和58年)に発表され、素材、軽さ、デザイン性、クオリティの高さは、30年以上支持されています。基本的なデザインを変えず、細かい部分でマイナーチェンジしながら、機能性、耐久性に関わる箇所を改良し、学生からサラリーマンそしてシニア層に至るまでの幅広い世代に、愛用されているそうです。
この本は、吉田カバンの代表取締役社長である吉田輝幸氏(吉田カバン創業者吉田吉蔵の次男)の著書で、創業80年の吉田カバンの姿勢や仕事の進め方、吉田カバンの品質を支える各部門のプロフェッショナルな職人さんたちなどについて書かれています。書名の「吉田基準」とは、社訓や品質基準マニュアルではなく、製造に携わる職人さんたちから自然発生的にできた言葉で、「吉田クオリティ」、「吉田らしさ」と言われることもあるということです。
その「吉田基準」とは何なのか。それは、吉田カバンでは、チームワークのとれた日本国内の職人さんが、よりよい商品を作り上げるためにデザイナーと真剣勝負を繰り広げながら手作業で生産し、メイドインジャパンを貫いていることです。また、基本的に値引きはせず、「商品が語ってくれる」と広告を出すことはせず商品説明に力を注ぎ、継続販売の姿勢を続けることで、ロングセラーを生み出していると述べています。
この吉田カバンのいろいろな経営手法のこだわりも紹介されていますが、たとえば、創業以来自社工場をもたず、商品は国内48か所にある工房で製作されており、多くは自宅兼作業場で1人2人で製作しています。そのため職人に余計な負担を増やさないよう、商品にバーコードをつけないことなど、商品づくりに何よりも優先順位をおいています。
この本から、長く世代を超えて愛される商品を世に出し続けている会社の、ものづくりへのプロ意識を知ることができます。「吉田らしさ」は「もっとクオリティをあげるものづくり」であり、その「ひとづくり」であること、その信念はすべての仕事に通ずる「基準」であると思います。ぜひ、カバン屋としてどうあるべきかを考える姿勢と心意気を、感じていただければと思います。
公開日:2015年11月17日
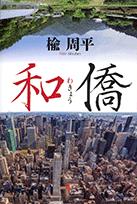 『和僑』楡 周平/著、祥伝社
『和僑』楡 周平/著、祥伝社
著者の楡周平は1957年生まれで、米国系企業在職中に執筆したデビュー作『Cの福音』(1996年 宝島社)は30万部を超えるベストセラーとなりました。翌年から作家に専念し、『猛禽の宴 続・Cの福音』(1997年 宝島社)、『フェイク』(2004年 角川書店)、『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・東京』(2008年 講談社)など、ミステリーや経済小説を中心に執筆しています。
この小説は、2008年に出版された『プラチナタウン』の続編です。
出世街道から落ちこぼれた総合商社部長の山崎鉄郎が、やけになって故郷宮城県緑原(みどりはら)町の町長を引き受け、老人向け定住型施設プラチナタウンの誘致に成功します。
人口が15,000人を切っていた緑原町にプラチナタウン開設で8,000人が入居し、新たに600人の雇用が生まれました。財政破綻寸前だった町は見事に回復し、シャッター通りとなっていた商店街も賑わいを取り戻していました。プラチナタウンのお蔭でUターンも増え、過疎高齢化問題も解決したかのように見えました。
しかしプラチナタウン開設から4年、町は危機を脱したものの、町の活況がプラチナタウンに依存しているという構図ができ上がっており、将来を見据えた新たなビジョンを確立することが必要となります。独居老人の増加、町の主要産業である畜産業に襲い掛かるTPP、農業従事者の高齢化と後継者不足、耕作放棄地と空き家問題、そしていずれやってくるであろう高齢者人口の減少といった課題がある中、町議会はその対応策として従前どおりの考え方でプラチナタウンの事業拡張を提案しようとします。それを打開し、町が生き残るための方策として思いついたのがB級グルメの緑原ブランド確立と海外進出でした。優秀な産業振興課課長の工藤登美子をパートナーに、緑原町の現状を見つめ熟考を重ねる山崎。そしていよいよ計画実行となったとき、彼はある決断を下します。その決断とは......。
様々な困難を克服していく様子は上手くいきすぎる感じも受けますが、実社会の問題も織り交ぜながらテンポ良く書かれており、一気に読み進めることができます。前作の『プラチナタウン』を読んでいなくても充分楽しめます。また、町を活性化させるために何を誰にどう売るのかを考えていく過程は、実際にビジネスプランを練るうえで参考になりそうです。
ぜひ、読んでみてください。
公開日:2015年10月15日
 『"ひとり出版社"という働きかた』西山 雅子/編 河出書房新社
『"ひとり出版社"という働きかた』西山 雅子/編 河出書房新社
「『小商い』と呼ばれるかたちで届けられたものやサービスが、私たちの生活を豊かにしています。自分の信じる仕事を、自らの責任で、信じる人々とのつながりを築きながら成立させようとするビジネス。それは自分らしい働き方を実現するひとつの方法として、広がりをみせています。」
編者のこの「はじめに」の言葉にあるように、大手企業の商品やサービスだけでなく、その隙間を埋める小さなビジネスの成果があるからこそ、世の中は充実し、また、そのような働き方をすることで、その人の人生も充実していくのでしょう。
この本は、一人で本を出版しようと立ち上がった10社の「ひとり出版社」と呼ばれる人々を取り上げ、彼らがこの道に入った経緯や、これまでどのような仕事をしてきたのか、また、この仕事を通して、何を表現したいのかをまとめたものです。
「子どもと一緒に晩御飯を食べるため」、「本質的に必要なことを見極め、自分らしく生きていくため」など「ひとり出版社」を始めるきっかけはそれぞれです。出版や編集の経験の有無、どのような本を作り、それをどのように流通させているかも、様々な形があります。
ただ、共通しているのは、効率的に利益を生まなければならない大手出版社が作る本とは異なる本を作ること、そして、その本の魅力を誰かに伝えたいという強い思いがうかがえることです。
大手出版社が作ることのできない個性的な本にも、必ずその読者はいます。また、インターネットの普及により、出版や流通の仕組みも大きく変わり、大手取次を通さなくても、読者に本を届けることができるようになりました。
「ひとり出版社」はその小ささを生かし、作りたい本を作り、それを求める書店や読者とつながり、日々の仕事をしています。
働き方は生き方です。
この本は、自分の仕事を振り返り、生き方についても考えるきっかけとなる一冊です。