公開日:2019年01月17日
 『世界基準のビジネスエリートが実践している 最強の体調管理』中根 一/著 株式会社KADOKAWA
『世界基準のビジネスエリートが実践している 最強の体調管理』中根 一/著 株式会社KADOKAWA
身体のパフォーマンスが下がると、20代、30代でも疲労感が出てきます。40歳を超えたあたりから、ある一定の体質に偏っていく傾向があり、これが「老け込む」ということだと著者は述べています。
著者は東洋医学を専門とする鍼灸師であり、その立場から、「老け込む」ことへの対処法を「食事」「休息法」「生活習慣」に分け、様々な方法を紹介し、自分自身の身体の状態にあった「オーダーメイドの体調管理」ができるよう解説しています。
第2章「常に調子よくあるための最強の『食事』」では、昨今、糖質を摂ることを避けがちになっていますが、「糖質制限」よりも「満腹にならないこと」が大切で、考える仕事には糖質は必須であり、「頭脳労働者」にとっては糖を抜きにして、いい仕事はできないと説明しています。また、「朝の緑茶」はコーヒーの10倍パフォーマンスを上げるなど、簡単に身体を整える方法も紹介してあります。
第3章「一流と二流を分ける最強の「休息法」」では、正しい休息をとることが基本であり、その休息に必要なものとして睡眠を挙げ、睡眠をとっても疲れがとれない原因として、身体を修復する「成長ホルモン」の分泌量の減少を指摘しています。睡眠中の成長ホルモンの分泌を促すには「就寝する2時間前に、5分間だけ軽い筋トレ」を行うことが有効であり、その筋トレ方も示しています。
この本には生活に取り入れやすいものが多くあります。自分に合ったものを取り入れ、身体のパフォーマンスを上げる体調管理を行い、老けない身体を目指してみてはいかがでしょうか。
公開日:2018年12月19日
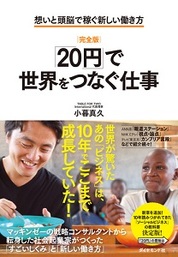 『〔完全版〕「20円」で世界をつなぐ仕事-想いと頭脳で稼ぐ新しい働き方』小暮 真久/著 ダイヤモンド社
『〔完全版〕「20円」で世界をつなぐ仕事-想いと頭脳で稼ぐ新しい働き方』小暮 真久/著 ダイヤモンド社
著者の小暮真久氏は、「企業の社員食堂にカロリーを抑えたヘルシーメニューを加えてもらい、その代金のうちの20円が開発途上国の子どもたちの給食一食分として寄付される。そのことで、貧困とメタボリック・シンドロームという二つの社会課題を同時に解決することを目指す」というコンセプトで、2007年にNPO法人TABLE FOR TWO International」を立ち上げました。その2年後の2009年に本書の旧版を執筆・出版しています(2010年度ビジネス書大賞新人賞(ビジネス書大賞実行委員会/主催)を受賞)。
活動は、当初の多くの給食を供給することから、少しでもおいしいものを届ける、そして体にいいものを届けることに変わっていき、地元の自立を促す取組も行っています。
前書から10年間の活動が「どこまでたどりつけたのか。そして、本当に新しい働き方を示すほどの成果を出し続けられているのか。」についてを書き加えられており、試行錯誤しながら活動を広げている姿が伝わってきます。
日本では、社会事業の歴史は浅く「社会事業なんて仕事じゃない」「善意のある人が無償でやるべきこと」という見方が多い中、著者が何を考え、具体的にどのように「しくみ」を考え仕事をしているのか、また社会事業をビジネスとして行うことについてわかりやすくまとめられています。
「今の仕事が天職だ」と語る著者の「想い」を感じると共に、「社会起業家」として働くとはどういうことなのかを考えることのできる一冊です。
公開日:2018年11月18日
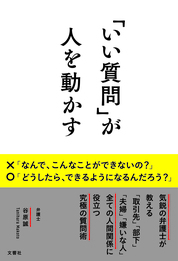 『「いい質問」が人を動かす』谷原 誠/著 文響社
『「いい質問」が人を動かす』谷原 誠/著 文響社
近代物理学の祖、ニュートンは「なぜリンゴは落ちるのか?」という問いから、万有引力を発見し、物理学に進歩をもたらしました。自動車の組み立ては、昔は一か所で作業員が入れ替わり立ち替わり来て、順次組み立てていましたが「人間が移動するのではなく、車が移動することができないか?」という問いから、ベルトコンベヤー式の自動車組み立て方法が発案されました。
このように、人は質問を発し、その答えを求めることにより、文明を発展させ、快適な生活を実現させてきました。
本書では、裁判で証人尋問を行うなど「質問のプロ」とも言える弁護士である著者が、質問の持つ大きな力について、さまざまな事例から、わかりやすく伝えてくれます。
質問をされると、人はその質問に答えようとして、考え、そして答えを出します。この質問による「①思考」と「②答え」の強制力という2つの機能により、情報を得たり、人を育てたり、自分をコントロールするなどの6つの力を手にすることができると著者は言います。
第1章「知りたい情報を楽々獲得する6つのテクニック」では、何を目的とするかを明確にすることの重要性や、質問を始める前にチェックするべきポイントなどを知ることができます。
第2章からは、聞くだけで人に好かれたり、人をその気にさせたり、人を育てることができる「いい質問」について学ぶことができます。
最終章の第6章では、"自分を変える「いい質問」"というテーマで、仕事や日常生活で役立つ様々な質問のテクニックを、自分に対して生かす「質問ワーク」もあります。
章の終わりごとには、ポイントをまとめたシートもあり、各章での学びを自分でフィードバックすることもできます。
「質問する力」を高めることは、人間理解を深め、さらには自分自身をよい方向に変え、人生で成功する力を身につけることに等しいということを、さまざまな事例を通して実感させてくれる本です。
公開日:2018年10月24日
 『行こう、どこにもなかった方法で』寺尾 玄/著 新潮社
『行こう、どこにもなかった方法で』寺尾 玄/著 新潮社
この本は、「そよ風の扇風機」として、ドラマに登場し話題となった製品の開発秘話に協力したバルミューダ株式会社 代表取締役社長 寺尾 玄氏が、山あり谷ありの多彩な人生を書いたものです。
「無茶で情熱的」そして「偉大な」両親の話、父や母からの教えやすすめられた本・映画の話、自然の中での暮し、不良仲間とバイクで走った高校時代、高校を辞めて、スペイン・イタリア・フランスを旅した話、ロックスターを目指した時代、そしてものづくりに新たな夢を見出し、ヒット商品を生みだすまで、まるで小説のように語られています。
数々の驚きと失敗の中で、根底にあるのは、両親からの「いつでも真剣に生きること、常識にとらわれずに自由に考えること、本気で夢を信じていいこと」という教えです。そして、全く知識も経験がなくても、行動を起こして、自分で本を読んで勉強し、その情熱を伝えることで協力者を見つけ、ぎりぎりの状況からチャンスを掴んでいきます。
寺尾氏がものづくりを仕事にしたいと思い、製作所を回り、会社を立ち上げ、こだわりの商品を生み出すまでの怒涛の日々は、リスクを負いながらも、世界中の人が欲しがると信じて、夢にすべてをかけての挑戦の連続です。
「人生は切り開くことができる。いつでも、誰でも、その可能性を持っている」という信念をストレートに伝える一冊です。
公開日:2018年09月19日
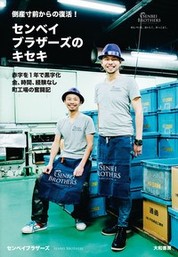 『センベイブラザーズのキセキ』センベイブラザーズ/著 大和書房
『センベイブラザーズのキセキ』センベイブラザーズ/著 大和書房
「センベイブラザーズ」は東京で4代続く煎餅工場、笠原製菓が展開する小売ブランドです。
1959年、著者の祖父母が「笠原煎餅屋」を立ち上げ、父、叔父がその跡を継ぎましたが、病に倒れてしまいます。2014年、兄が家業を継ぐ決断をし、弟が煎餅を焼いて、兄が売るセンベイブラザーズが誕生します。兄弟が家業を継いだ時に、経営は倒産寸前の危機的な状況でした。
「金なし、時間なし、経験なし」で始まったセンベイブラザーズですが、工場直売から始め、駅での販売、催事場、ブランドとのコラボレーションと販路を拡大します。2015年からは「せんべいを、おいしく、かっこよく。」をコンセプトに掲げ、今では入手困難な人気煎餅屋です。
工場直売を始めた時には、どのような目的で購入されるのかそれまで知らなかった隠れたニーズに気づき、催事場の経験では、その場では良い結果が残せなくても、次につながる足跡を残すことの大切さを学び、家業に入る前にしてきた様々な仕事もどれ一つ欠けても今には至らなかったと著者は述べています。
煎餅職人である弟は、受注生産をしていた頃には「怒られない仕事をやろう」という心持ちでしていたが、自分たちで考え、直接販売するようになり、胸を張って「煎餅職人」と言えるようになったと述べています。
様々な経験は全て今につながり、仕事を自分の事として行い、自信をもって続けることが大切というセンベイブラザーズの経験は、どの仕事においても参考になるのではないでしょうか。
公開日:2018年08月17日
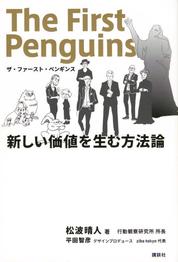 『ザ・ファースト・ペンギンス 新しい価値を生む方法論』松波 晴人/著 講談社
『ザ・ファースト・ペンギンス 新しい価値を生む方法論』松波 晴人/著 講談社
新しいビジネスを始めようとする時や、企業の中で新しいモノやサービスを考え、提供する時にまず求められるものは何でしょうか?
それは「新しい価値の創造」です。
本書では「新たな価値をどうすれば発想できるか?」、「誰もが初めて聞くような画期的な新価値を、組織でどうやって意思決定するのか?」という2つの壁を乗り越えるために必要な、「気づき」、「アブダクション(仮説的推論)」、「統合」といった8つの理論を物語と絵で説明しています。
フィリップ課長から、「会社の将来を支える新しい価値の創造を、君が担当してくれないか?」と指示を受けた若手社員ジョージ君は、仲間とともに悪戦苦闘しながら、これらの理論を学んでいきます。
「新たな気づきを得る」から、「これまでと違う行動を取る」までを自分であればどのように取り組むか、一緒に考えてみてはいかがでしょうか。
公開日:2018年07月31日
 『知的戦闘力を高める 独学の技法』山口 周/著 ダイヤモンド社
『知的戦闘力を高める 独学の技法』山口 周/著 ダイヤモンド社
仕事や活動など多忙な中、何かを学びたいとき、自分のペースでできる「独学」を選択する人は多いと思います。本書では、独学で外資系コンサルタントになった著者が、自身が構築した知的戦闘力を向上させることができる「独学の技術」を、詳細にわかりやすく伝えてくれます。
まず大切なのは、独学を「システム」として捉えることで、そのシステムは大きく①戦略、②インプット、③抽象化・構造化、④ストックという4つの要素で構成されます。
限りある時間の中で、何をインプットするのか、何をインプットしないのかを決める「戦略」を立て、本やネットに限らず様々なソースから、自分の五感を通じて「インプット」する。さらにインプットした情報について、細かい要素は捨て本質的なメカニズムだけを抽出する「抽象化」、他のものと組み合わせたりして独自の視点を持たせる「構造化」を経て、「ストック」した上で、ストックした知識を引き出せるシステムを作るところまでを、具体的な事例や先達たちの言葉も織り込みながら、くわしく説明しています。
身の丈に合ったインプットを心がけること、自分らしい「問い」を持つことの大切さなどにも触れていて、例えば「問い」を持つことで人間や世界に対する理解や関心が深まり、ビジネスに関連するものの見方にも新しい刺激を与えてくれるとも述べています。
最終章となる第5章「なぜ『知の武器』になるのか?」では、教養を高める有用なジャンルとして、"リベラルアーツ"と呼ばれる歴史、心理学、音楽、文学など11ジャンルを挙げ、それぞれお薦めの書籍も紹介されています。
「独学の技術」を磨くことは、よりよい仕事につながるとともに、しなやかな知性を育み、それが本当の意味で豊かな人生につながることを気づかせてくれる本です。
公開日:2018年06月21日
 『本のエンドロール』安藤 祐介/著 講談社
『本のエンドロール』安藤 祐介/著 講談社
この本は、本造りに携わる印刷会社の営業、工場作業員、DTPオペレーター、デザイナー等を取り上げた小説です。著者は、2015年5月から約3年、実際に多くの印刷会社の人々に取材して、それぞれの仕事の工程や背景を丁寧に聞いて描いています。ペーパーバックや電子書籍と印刷会社の関わり等、業界の展望にも触れています。
主人公の豊澄印刷株式会社営業部の浦本学は、顧客である出版社と打ち合わせし、印刷所の状況等をみながら、全体を調整する役割を果たしています。その彼が会社説明会で就活生に将来の夢について聞かれた時に、「印刷がものづくりとして認められる日が来ること」と答えます。本はまず作家が原稿を書き、編集者が出版の企画を立て、デザイナーと相談して本の仕様が決まるが、印刷会社や製本会社は本を刷るのではない。本を造る「メーカー(ものづくり)」であり、夢と責任のある仕事だとも話します。浦本がこの言葉の持つ意味を自問自答していくことからこの物語は始まります。それに対峙して、同じ営業部の仲井戸光二は、夢は「目の前の仕事を手違いなく終わらせること」「印刷機の稼働率を上げること」と答えます。浦本は考え方の違いから仲井戸に反発しながらもよき先輩として一目置いています。このふたりが仕事の様々な困難な場面で真剣にぶつかりながらも、次第にお互いを認め合うようになっていくところは圧巻です。
本造りの現場がわかると、多くの人の思いの詰まったものとして、「本」をより身近に感じられるようになります。
「どう仕事をするかは、どう生きるかに等しい」と、好きな本造りに挑む主人公は語っています。仕事にかける熱い思いを感じながら楽しめる一冊です。
公開日:2018年05月16日
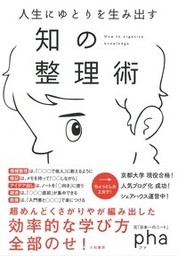 『人生にゆとりを生み出す知の整理術』pha(ファ) /著 大和書房
『人生にゆとりを生み出す知の整理術』pha(ファ) /著 大和書房
「僕は小さい頃から、ほとんど何かをがんばったことがない。」という著者のphaさんは、京大に現役合格し、就職後28歳で会社を辞め、無職の生活をされていました。その間ブログが人気になり、5年間で5冊の書籍を出版し、現在はシェアハウスの運営もされています。
著者は「大体のことはなんとなくやっているうちにうまくいった。」と述べ、その理由として人生の早い段階で勉強を楽しむやり方を身につけることができたことを挙げています。この本では著者の「がんばらずに、なんとなくうまくいく勉強法」の実践方法が書かれています。
例えば、第1章「情報を整理するインプットの技術」では、自分の興味がない分野の勉強をしなくてはいけない時の方法が紹介してあります。まずは興味を持つために「それをおもしろがってやっている人を見ることで、その世界の空気をつかむことを目指そう。」「そのジャンルの専門用語を覚えるのもいい。」そして、「知識をかきまぜる」ように本を3冊読み、「牛の消化」みたいに何度も反芻して覚えると書かれています。また、すぐに実践できそうな「読書メモ」の取り方も紹介してあります。
第2章「頭を整理するアウトプットの技術」では、言語化することの重要性、知識を自分のものにするコツ、アイデアの出し方などが書かれています。著者の実体験をもとにした「ブログの読者」獲得法にも触れています。
年度が替わり、新しいことを覚えなくてはならない場面もあると思います。"なんとなく"うまくいく勉強法を使い、覚えることを楽しんでみてはいかがでしょうか。
公開日:2018年04月25日
 『調べるチカラ』野崎 篤志/著 日本経済新聞出版社
『調べるチカラ』野崎 篤志/著 日本経済新聞出版社
インターネットが普及して既に20年近く経ち、検索エンジンに調べたい情報に関するキーワードを入力すると、大量の情報が提示されるという、便利な時代になりました。ただ、あまりにも情報が多く、その中から、本当に必要で信頼できる情報を見つけ出すにはどうすればよいのか、迷うこともあると思います。
本書は、情報があふれている「情報過多時代」において、欲しい情報を効率的・効果的に調べるスキルを身につけるための入門書です。知財情報コンサルタントとして活躍する著者から、どのような情報源を調べれば良いか、また検索エンジンを使うための具体的なテクニック、さらに、情報収集するために最も重要な「情報感度」を磨く方法などをわかりやすく学ぶことができます。
第2章「情報感度は誰でも身につけることができる」では、「調べるチカラ」をつけるための情報ネットワークを、①インターネット、②新聞・書籍など、③人に整理し、この3つの情報ネットワークをバランスよく使い分けることが必要であると述べています。さらにこのことは、第4章「インターネットで調べる」、第5章「インターネット以外のネットワークから調べる」で詳しく説明されています。
第5章の中では、情報感度を磨くためには「人」とのつながりが大切であり、まず家族や同僚などの身近な人とのコミュニケーションから情報収集をはじめることが提案されています。そして、人とのつながりを継続するには、自分自身も情報を発信していくことの重要性に気づかされます。
情報収集スキルは、ビジネスパーソンだけではなく、個人としての夢や目標を実現するためにも役立つ必須スキルである、と著者は言います。「調べるチカラ」を高め、さまざまな場面で情報を活用することは、より豊かな人生を送ることにつながるのではないかと思わせてくれる本です。