公開日:2019年11月28日
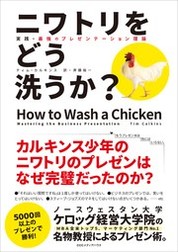 『ニワトリをどう洗うか?実践・最強のプレゼンテーション理論』ティム・カルキンス/著 斉藤 裕一/訳 CCCメディアハウス
『ニワトリをどう洗うか?実践・最強のプレゼンテーション理論』ティム・カルキンス/著 斉藤 裕一/訳 CCCメディアハウス
著者のティム・カルキンス氏は、ノースウェスタン大学ケロッグ経営大学院教授で、優れた教員として、教育活動で数多くの賞を受賞しています。彼は、8歳(1973年)のときに、「ニワトリの洗い方」という初めてのプレゼンテーションをコンテストで行って以降、5,000回以上のプレゼンテーションをこなしてきました。
この本では、著者がこれまで見てきた、教え子たちのプレゼンテーションでの失敗場面を基に、効果的なプレゼン術について紹介しています。また、自身の経験から得た、プレゼンの伝える力とそのスキルを高めるための方法について実践だけでなく理論についても書かれています。
具体的には、プレゼンの事前準備、内容、リハーサル、会場セッティング、そしてプレゼン中の行動、質問への対応やフォローなどについて基本から実践までの方策について述べています。また、「プレゼンテーション」という言葉から、学生がすぐに思い浮かべるという「TEDトーク」や、スティーブ・ジョブズのプレゼンについても触れ、ビジネスのプレゼンの場面にはそぐわないとしながらも、そこから学ぶことができるそれぞれのメリットについても説明しています。
著者は、優れたプレゼンテーションは、「人々の意見を変えさせ、支持や承認を得ることにつながりうる」ので、プレゼンのスキルが高まれば、確実に仕事の成果も向上するといいます。
プレゼンテーションは、ビジネスの様々な場面で、重要なスキルです。ぜひ、読んで実践する参考にし、効果的なプレゼンテーションの力を体感してみてください。
公開日:2019年10月16日
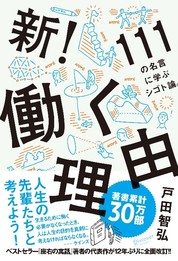 『新!働く理由 111の名言に学ぶシゴト論。』戸田 智弘/著 ディスカヴァー・トゥエンティワン
『新!働く理由 111の名言に学ぶシゴト論。』戸田 智弘/著 ディスカヴァー・トゥエンティワン
著者は「仕事が面白くなかった」ため会社を3年間で辞め、資格取得や転職を重ねて、現在はフリーランスのライターやキャリアカウンセラーなどをされています。そのキャリア形成の中、仕事に関して悩んでいた時期に、著者が出会った心理学者ドナルド・E・スーパーの言葉で長年の霧がひとつ解けたような気がしたと述べています。
今働いている人や、これから働こうとしている人が働く理由を考える時は、不安であったり不満であったり何らかの思いを抱いているのではないでしょうか。著者はそのような時に働くということについて、一人で考えるのではなく人生の先輩たち(の名言)と心の中で対話しながら、思いをめぐらすことを勧めています。
この本は、1章では「ただ生きること」×「よく生きること」、2章では「〈好き〉を仕事にする」×「仕事を〈愛する〉」、などのように15章に分類し、111人の名言を解説しています。本書の中には時代もジャンルもさまざまな人たちの言葉や考えが詰まっています。
自分の今の仕事や、働きたいと思っている仕事に対して向き合うきっかけとなる言葉や、自分自身が感じていることを代弁したかのような言葉に出会えるかもしれません。
公開日:2019年09月25日
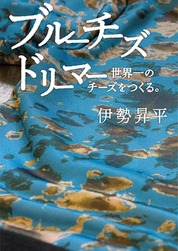 『ブルーチーズドリーマー 世界一のチーズをつくる。』伊勢 昇平/著 エイチエス
『ブルーチーズドリーマー 世界一のチーズをつくる。』伊勢 昇平/著 エイチエス
北海道旭川市江丹別(えたんべつ)に住む著者の伊勢さんは、自分だけの肩書きとして「ブルーチーズドリーマー」と名乗り、「世界一のチーズを故郷の江丹別でつくる」ことを目指しています。この本は、彼の夢、世界一のチーズづくりの奮闘記です。
伊勢さんは、両親が江丹別で牧場の仕事をしていたことから、街の高校に通っていた頃、「どうやって街まで来てるの?馬?」などと言われ、悔しい思いをしたといいます。いつか世界に出て、かっこいい場所でかっこいい仕事をして偉い人間になってやる!と、英会話を習いはじめます。ある日、英会話の先生から「お前の親父は牛乳絞ってんだろ。じゃあその牛乳でめちゃくちゃ美味いチーズをつくったら、それだって立派なワールドワイドだぞ」と言われます。その言葉に衝撃を受け、世界一と呼ばれるチーズをつくることを考えるようになったそうです。
チーズ工房で見習いをしていた時、同じ製法でも原料が異なるチーズを食べ比べて、父の牛乳へのこだわりがチーズに活かせることに気付きます。そこで、世界のチーズの産地で江丹別と同じ気候の土地を調べると、ブルーチーズが有名なフランスのオーベルニュという地方があてはまりました。普通はリスクを分散させるため何種類ものチーズを作りますが、一週間の視察の帰国後は、一つのことを極め高め自分の夢を叶えようと、製造はブルーチーズのみと決意します。
チーズを販売できるようになってからも、青カビが生えないという事件が起こりました。季節の変化によってミルクの成分が変化した時に、上手くいかなくなるらしいのですが、原因がわからず、多くを廃棄して3年間を過ごすことになります。発狂しそうなほどの絶望の淵から、気持ちを入れ替えて、フランスで飛び込み修行をし、必要な知識と技術を学び再出発をします。
この本では、夢を叶えるために何をどう選択してきたか、自分の思いをどのように発信していくか、ブルーチーズづくりを通して経験した人生観、ものづくりのノウハウが詳細に書かれています。
「己の気持ちに正直であれ、だれもがみんなドリーマー!」の巻末の言葉が力強く伝わってきます。
公開日:2019年08月16日
 『一瞬の出会いでチャンスをつかんでいる人の顔グセの法則』重田 みゆき/著 ダイヤモンド社
『一瞬の出会いでチャンスをつかんでいる人の顔グセの法則』重田 みゆき/著 ダイヤモンド社
「幸せだから笑うのではなく、幸せになるために笑うんです」と著者はいいます。
この本の著者は印象評論家として活躍している重田みゆきさんです。
本の表紙から著者の抜群の笑顔が伝わってきます。
著者は「見た目の印象で、損をしている人は意外と多いものです。私が今まで出会ってきた9割の人が「損な笑顔」をしていると言っても過言ではないかもしれません。正確にいうと本人は笑顔のつもりでもそれが笑顔に見えていない人がほとんどです。」と述べています。
本書ではいい笑顔のクセ「顔グセ」によってチャンスをつかんだ人たちのストーリーや、いい「顔グセ」のポイント、トレーニング方法、さらに笑顔を活かして一瞬の出会いで相手の心に残るテクニックが紹介されています。
また「いい顔グセ」に変えることの大きなメリットとして「心まで大きく変わること」を挙げています。
心理学や脳科学の世界では、笑顔にすることで動く筋肉が顔のツボを刺激し、脳にリラックス効果のあるアルファ波を出します。そして副交感神経が活発に動き始めることで自律神経のバランスもとれ、明るく前向きな考え方や、元気に活動しようとする力が湧いてくるのだそうです。
本書の最後には笑顔の確認ができるチェックリストもついています。
トレーニングは4種類。1日3分の隙間時間に取り組める手軽なトレーニングばかりです。「笑う門には福来る」ともいいます。顔グセトレーニングでこれから待っているチャンスをつかんでみませんか?
公開日:2019年08月11日
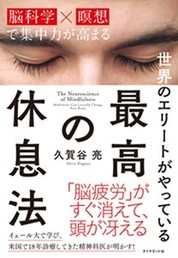 『世界のエリートがやっている最高の休息法』久賀谷 亮/著 ダイヤモンド社
『世界のエリートがやっている最高の休息法』久賀谷 亮/著 ダイヤモンド社
「いつも疲れている、どれだけ休んでもなんとなくダルい、集中力が続かない、いろんなことが気になる...」
そんな人は、身体ではなく、脳が疲労しており、脳には脳の休め方があるのだそうです。
本書は、イェール大学で先端脳科学研究に携わり、日米で臨床医として25年以上のキャリアを持つ著者が、「マインドフルネス」の持つ効果を、脳科学的な知見も交えながら伝えています。
マインドフルネスをひと言で説明すると、「瞑想などを通じた脳の休息法の総称」です。現在ではグーグルなどの著名な企業でも、マインドフルネス研修が社内の仕組みとして取り入れられています。
助走パート「脳の疲労を解消する7つの休息法」では、マインドフルネス瞑想のアウトラインを掴むことができます。
本編「マインドフル・モーメント-最高の休息法の物語」では、マインドフルネスが脳科学の最前線とどのように関わっているかを、イェール大学精神神経学科の日本人研究員ナツを主人公に物語形式で語られています。架空の物語ですが、引用している研究成果は事実であり、巻末には参考文献一覧の掲載もあります。
また、特別付録パート「アメリカ精神科医がおすすめする5日間シンプル休息法」は、これからの夏休みや年末年始など、長期休暇を過ごす時の参考になりそうです。
「瞑想」、「マインドフルネス」という言葉は、いろいろなメディアで取り上げられていますが、この本を読むことで、科学的にどのような効果があるのか、どのように行えばよいのかを理解することができます。実践してみてはいかがでしょうか。
公開日:2019年08月08日
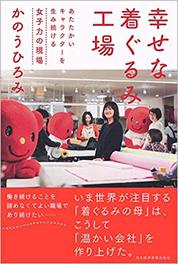 『幸せな着ぐるみ工場』かのう ひろみ/著 日本経済新聞社
『幸せな着ぐるみ工場』かのう ひろみ/著 日本経済新聞社
この本の著者は、宮崎市にある工場で、着ぐるみのデザイン・制作を手掛ける「KIGURUMI.BIZ」の代表取締役 かのうひろみ氏です。「正しい商品は正しい場所から生まれる」という信念のもと、自分たちの工場で生まれる着ぐるみを「手塩にかけて育てる」とし、母親のように愛情を込めて作っていることが、ひしひしと伝わってきます。
「思い出深いキャラクターたち」の章では、佐賀県の唐津城築城400年を機に誕生した犬の「唐ワンくん」や、みやざき県のシンボルキャラクター「みやざき犬」などを制作したこと、また、「毛ガニ君」や「ゴーヤ先生」の活躍をとおして、震災のときのキャラクターの持つ力について考えたことを述べています。
そして、今では台湾やイタリアなど世界中から仕事の照会が届き、この工場から海外に渡った着ぐるみは70体を超え、輸出先の国・地域の数は15にも及んでいるそうです。
著者は、シングルマザーで子育てをしながら仕事をし、その後再婚で宮崎に戻ります。仕事のパートナーである夫とふたりで、アートをビジネスにし、需要の増えてきた着ぐるみに絞った会社を作りました。
この会社は女性ばかりの職場で、「女性が働く」ということの様々な難局に、自分の苦労した経験を活かして、スタッフの意見を聞きながら残業も休日出勤もないなどの労務管理や働き方の改革にチャレンジし、女性の特性や女子力を活かして、幸せな会社づくりを実践しています。それが最後の「幸せな着ぐるみは、絶対幸せな工場からしか生まれない」という言葉に詰まっています。
仕事やスタッフそして着ぐるみにかける信念、仕事に前向きに取り組むことで得られる幸せな思いを存分に感じることができる一冊です。
公開日:2019年05月16日
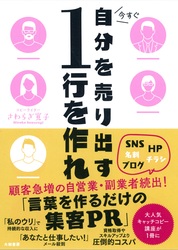 『今すぐ自分を売り出す1行を作れ』さわらぎ 寛子/著 大和書房
『今すぐ自分を売り出す1行を作れ』さわらぎ 寛子/著 大和書房
初めて会った人に「自分が何者か、誰にどんな価値を提供できるのか」を伝える言葉を持っていますか?
本書では、会社員、起業を目指す主婦、フリーランスのウェブデザイナー、美容師の4人との対話形式で、自分が持っている売り、あるいは自分が売り込みたい部分を1行で(あるいは短く)効果的に伝える「自分のキャッチコピー」を作るための考え方・手順などの、メソッドがまとめられています。
著者は、キャッチコピーとは思いつきや言葉が降ってくるのではなく、自分が何を得意とし、相手にどんなメリットがある人間なのか考え、それらを数多く書き出し言語化するという、自分がどういう人間かを棚おろしする「けっこう面倒くさいというか時間がかかる」作業を行うことにより、「自分を売り出す1行」を作り出すのだと述べています。
そうして作り出した「自分を売り出す1行」は、自分の指針となる、と著者は言います。
この本を読み、この一連の作業をすることで、今ある自分やこうありたい自分が見えてくるきっかけになるかもしれません。
公開日:2019年04月16日
 『伝わるしくみ』山本 高史/著 マガジンハウス
『伝わるしくみ』山本 高史/著 マガジンハウス
「「伝えたい」気持ちをなんとかしたい」、この一文から本書は始まります。著者は20年以上コピーライターとして活躍し、数多くの賞を受賞し、現在、関西大学社会学部の教授を務めている山本高史さんです。
本書は、「伝えるフローチャート」をもとにインプット、アウトプットに分け、伝わらない原因を4つ挙げ、各章でその解消法の提案がされています。
第1章「「言葉のメカニズム」を知る」では、「受け手という存在を認識・理解していない」ことが伝わらない原因の一つであると書かれています。普段はなかなか意識しないが、独り言や寝言やノートの落書きでもない限り、言葉を発すれば必ず自分は「送り手」になり、聞く側は「受け手」になる。その言葉は、自分の意図とは関係なく、受け手が受け入れるか、受け入れないかのすべてを決める。また、受け手は言葉に対して、無視、拒絶、同意の3通りをとることができるが、得になる「ベネフィット」があれば、同意する。ただ、ベネフィットは受け手の置かれている状況によって変化することを理解することが大事だと述べています。
第2章、第3章では、受け手の状況を理解し、伝えるための発想の訓練方法が具体例を使って解説してあります。
第4章「「言葉」の使い方」では、伝えるためには、言葉の持つ意味を共有することが必要であり、曖昧な言葉は、主観により理解されるため、避ける方がよいことが示されています。
新年度、新たな出会いも多い時期です。本書を読んで、「伝える」ということを改めて見直してみてはいかがでしょうか。
公開日:2019年04月11日
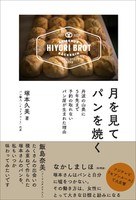 『月を見てパンを焼くー丹波の山奥に5年先まで予約の取れないパン屋が生まれた理由』塚本 久美/著 カンゼン
『月を見てパンを焼くー丹波の山奥に5年先まで予約の取れないパン屋が生まれた理由』塚本 久美/著 カンゼン
雲海の美しさで知られる、兵庫県丹波市氷上町。ここに通信販売専門の"旅する"パン屋「ヒヨリブロート」の厨房があります。
このパン屋を一人で経営する塚本久美さんは、大学卒業後、一般企業に勤めていましたが、パン職人の道を目指し退職、東京都世田谷区の「シニフィアン シニフィエ」で7年間修業生活を送ります。様々な人との出会いから、それまで縁もゆかりもなかった丹波市にひきよせられ、店舗を持たないパン屋をオープンさせます。
「ヒヨリブロート」の大きな特徴のひとつに、月の満ち欠けによってパンづくりのスケジュールを決めるというものがあります。パン作りを学んだドイツで出合ったもので、ドイツには月齢で農作物を育てる方法があり、パンづくりにおいても発酵の速度の変化などの影響があるとのこと。
月齢に合わせて20日間パンを焼き、10日間はパン作りを休み、食材の生産者を巡ることができるこのスタイルは、ユニークであるとともに、パン職人として働きながらも、食材探しの旅にも出かけたいという願いも叶えるものでした。
こだわりを持ちつつ、会社員時代の経験をいかし、ビジネスとして成立させるために、塚本さんはコスト意識も大切にしており、コストに対する利益率を考え、ふさわしい価格で売るために工夫を重ねています。また、パンを作らない時期には、パンを直接販売するイベントや異業種とのコラボも行っています。
26歳でパン職人としては遅いスタートを切り、遠回りをしたのではと悔やんだこともあったそうですが、今は何一つ無駄ではなかったと実感しています。
この本には、「ヒヨリブロート」で大切にしているパンづくりの考え方、食材の生産者とのつながり、働くという意味など、パン職人・塚田久美さんの働き方、生き方がつまっています。
同じパン職人の伴侶とも出会い、「パン職人夫婦」としての新しい試みも始めているとのこと、これからの「ヒヨリブロート」がますます楽しみです。
公開日:2019年02月16日
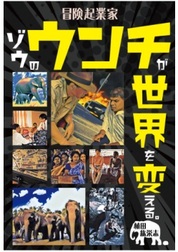 『冒険起業家 ゾウのウンチが世界を変える。』植田 紘栄志/著 ミチコーポレーションぞうさん出版事業部
『冒険起業家 ゾウのウンチが世界を変える。』植田 紘栄志/著 ミチコーポレーションぞうさん出版事業部
この本は、東京で偶然出会ったスリランカ人に1万円を貸したことをきっかけに、内戦が続くスリランカの国を巻き込んだ事業に挑んだパワーに満ちた起業家の実話です。
著者は当初、魚市場で働いてお金を貯めながら、中古機械の輸出ブローカーの会社を経営していましたが、スリランカ初のペットボトルリサイクル工場『ミチランカ』を創業します。そして様々なトラブルが起こるなかで、赤字続きのペットボトルのリサイクル工場の生き残りをかけて、紅茶ビジネス、宝石ビジネス、高級食材のフカヒレビジネスなど事業に挑戦しては失敗し、ぎりぎりの状況に追い込まれていきます。
しかし、工場が野良ゾウの襲撃に合ったことから、ゾウと人間の共存を考えるようになります。そこでゾウの糞でできた紙に、「ぞうさんペーパー」と名付け、起死回生を図ります。「ぞうさんペーパー」の工場をつくり、画用紙やノートやカードなど手作り文具を生産し、日本で積極的に営業活動を行い、ついには「ハンズ大賞」に選ばれるまでになりました。やっと軌道にのったところで発生した、ゾウの糞がワシントン条約に抵触するという問題も、諦めず自分の力で打開していきます。
また、著者は、田舎町で仕事がないことで、若者の多くが兵役を志願して命を落としてしまう厳しいスリランカの現実に直面し、スリランカの若者を一人でも多く雇用できる事業をめざすようになります。スマトラ島沖巨大地震や東日本大震災、そしてビジネスパートナーの死という次々と襲う苦難を乗り越えつつ、家族のことを守りたいという思いがつのり、祖父母が住んでいた限界集落への移住を考え始めます。
現在は、過疎の進む田舎町広島県山県郡北広島町に移住し、「ぞうさんペーパー」を作って販売しながら、「芸北ゾウさんカフェ」を経営し、変わらずリスクを恐れず新たなビジネスに挑戦し続けています。驚きと笑いや涙ありの元気が出る一冊です。