公開日:2020年09月15日
 『FACTFULNESS(ファクトフルネス)10の思い込みを乗り越え、データを基に世界を正しく見る習慣』ハンス・ロスリング、オーラ・ロスリング、アンナ・ロスリング・ロランド/著 上杉 周作、関 美和/訳 日経BP社
『FACTFULNESS(ファクトフルネス)10の思い込みを乗り越え、データを基に世界を正しく見る習慣』ハンス・ロスリング、オーラ・ロスリング、アンナ・ロスリング・ロランド/著 上杉 周作、関 美和/訳 日経BP社
ファクトフルネスとは、事実に基づいて世界を正しく見ることです。
著者ハンス・ロスリングは、スウェーデン人の医師、グローバルヘルスの教授で医療と公衆衛生に関する世界的権威であり、世界保健機構やユニセフのアドバイザーも務めていました。2017年に他界し、子息のオーラ・ロスリング、その妻アンナの両氏が原稿を整理補筆して本書に仕上げたということです。
この本では、人々が陥りやすい世界認識の誤りを、自らのドラマティックな体験も織り交ぜ、グローバル化・情報化が進んだ現代の状況に即して解説しています。
まず、冒頭で世界の事実に関する3択クイズ13問が出されています。1問目は、「現在、低所得国に暮らす女子の何割が、初等教育を修了するでしょう? A 20%、B 40%、C 60%」です。同じ13問で、2017年に行ったオンライン調査では、日本を含む世界14か国・1万2千人の平均正解数は、地球温暖化の質問をのぞけば、12問中たったの2問。全問正解者はいなかったということです。
この結果を招いた原因について、著者は、知識のアップデート不足とともに、人間の「分断本能」、「ネガティブ本能」、「恐怖本能」、「過大視本能」、「犯人捜し本能」など10の本能に関係があると分析しています。例えば、先のクイズに正解できないのは、「分断本能」つまり世界は分断されているという思い込みがあるためだと言います。
この本を読むことで、10の本能を抑える術を学ぶことでき、未来を予測して危機に対応できる新しい価値観が見つかるなど意識の変化を感じることができます。
世界の見方が変わることで、困難を感じている状況から一歩踏み出すきっかけになるかもしれません。
コロナ禍で、世界中が先の見えない不安に覆われている今だからこそ、読んでほしい一冊です。
公開日:2020年08月15日
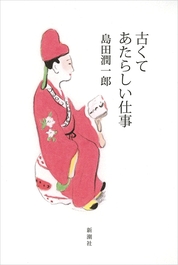 『古くてあたらしい仕事』島田 潤一郎/著 新潮社
『古くてあたらしい仕事』島田 潤一郎/著 新潮社
この本は、「夏(なつ)葉社(はしゃ)」という出版社を10年にわたり一人で経営する著者、島田潤一郎さんの誠実な仕事が書かれています。
著者が転職活動をしている最中に仲がよかった従兄が亡くなりました。それまでの生活が激変してしまった叔父と叔母に、自分が好きな一編の詩を本にして届けたいと思い知り合いに本の出版依頼をしますが、なかなか進展しません。そこで、一人で出版社をやってみようと考え、夏葉社を立ち上げました。
本の出版までに長い期間がかかりましたが無事に出版され、叔父と叔母を含め、多くの人に読まれているそうです。
著者は、会社を経営する上で人生の中で教わった言葉を支えに、お世話になった人たちに恩返しをしたいという気持ちで仕事に臨み、相手を信頼するという信念を持って接することを大切にしています。また、会社を続けていくコツは、できるだけ他社がやらない仕事をすることであり、小さな会社であれば何事にも手間暇をかけ小さな声に寄り添うための、より勇敢な選択をすることだと言います。
本の出版に関わる全ての人たちと真摯に向き合う著者が、彼らとともに「良い本を届けたい」という目標に向かって進んでいるからこそ、読者の心に届く本を生み出し続けているのではないでしょうか。今後のものづくりの可能性も感じられる一冊になっています。
公開日:2020年07月15日
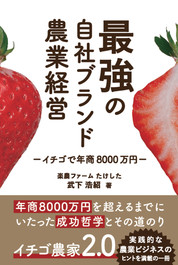 『最強の自社ブランド農業経営』武下 浩紹/著 秀和システム
『最強の自社ブランド農業経営』武下 浩紹/著 秀和システム
この本は、トマト農家からイチゴ農家に転換した後、産直イチゴ農家「楽農ファームたけした」を開業した著者の、新しいビジネス創造のチャレンジと自己変革の道のりが書かれています。
著者は、平成11年、26歳で実家のトマト農家に就農、平成14 年にイチゴ農家に転換しました。当時は、JAの苺部会に所属し、言われるがままに農作物を生産することで最低限の収入は保証されていました。しかし、最低限の収入に甘んじていたら10年後に希望が持てないと考え、「食えない農家」から脱出するためビジネスを学びます。農業をビジネスと捉え経営していくビジネス農家の道を歩み始めるのです。
高付加価値のイチゴを、どう育て、どうビジネスチャンスに繋げてゆくのか? 前半では、農家向けに具体的な実例や方法を紹介します。後半では、農家だけでなく、他の職業にも通じる、➀生産者側と購買者をつなぐWeb戦略 ②オフシーズン戦略 ③自社ブランド戦略と、武下流の成功哲学、例えば「いいものを作ったからといって、売れるとは限らない」「事業計画書が未来をつくる」「お客様によって磨かれる」といったことを指南しています。
現在、年商8000万円を超えるまでになった著者の、イチゴ農家は手段であり、自分の仕事を通じ人の成長を促進する技術が学べる、学んだことで人は変われるという揺るぎない自信と、「チャレンジには成功か失敗ではなく、成功か成長しかない」という熱い思いが詰まった一冊です。
公開日:2020年06月16日
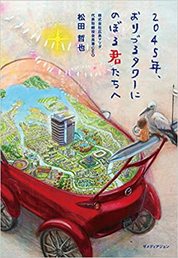 『2045年、おりづるタワーにのぼる君たちへ』松田 哲也/著 ザメディアジョン
『2045年、おりづるタワーにのぼる君たちへ』松田 哲也/著 ザメディアジョン
原爆ドームのすぐ近くに、2016年広島の新しいランドマークタワーとして誕生したおりづるタワーは、ビルの北向きの壁面に描かれた巨大な折り鶴の模様が目を引きます。
古いビルを取得しリノベーションして作られたこのタワーを「世界にひとつとして似たものがない唯一無二のタワー」だと、発案者で著者の株式会社広島マツダ代表取締役会長兼CEO 松田哲也氏は言います。
自動車販売会社の社長(当時)が、なぜ広島のこの場所に、何のために作ったのか。本書には、着想から完成までの経緯と細部までこだわり抜かれたタワーの様子、そこに込められた想いが丹念につづられています。
一方で著者は、自身の半生に触れ、おりづるタワーのもうひとつの見方を示します。おりづるタワーは、才能に恵まれた天才ではなく、自分のような負け続けた人生を歩んできた凡人が作った。だからこそ、自分と同じように周囲の期待に応えられない虚無感やプレッシャーを抱えてきた人たちに「やってやろうぜと言いたい」とエールを送ります。
そして、おりづるタワーのアイデアを考える中で、広島の街のグランドデザインにまで構想が広がっていったと述べる著者は、2045年、ちょうど被爆から100年後の節目の時を見据えます。どんな広島を次世代に渡したいのか、考えるのはそこに住む市民であり、今この時から考えていきませんかと私たちに投げかけています。
公開日:2020年05月15日
 『はたらくきほん100 毎日がスタートアップ』松浦 弥太郎/著 野尻 哲也/著 マガジンハウス
『はたらくきほん100 毎日がスタートアップ』松浦 弥太郎/著 野尻 哲也/著 マガジンハウス
この本の著者は、病気の予防・管理、ダイエットなどを目的とした管理栄養士監修のレシピ検索・献立作成サービスを提供している、(株)おいしい健康の共同CEOである松浦弥太郎氏と野尻哲也氏です。松浦氏はエッセイスト、クリエイティブディレクターとして活躍しており、2005年から2014年まで雑誌「暮しの手帖」の編集長を務め、2015年クックパッド(株)に入社。「くらしのきほん」編集長を経て、 (株)おいしい健康の共同CEOに就任しました。野尻氏は2004年に(株)UNBINDを設立し、代表取締役就任。2016年、クックパッド(株)からのMBO(Management Buyout)を経て、(株)おいしい健康を設立し、共同CEOに就任しました。
この本には松浦氏と野尻氏それぞれが今までの仕事での経験を通して確かめてきた「はたらくきほん100」と「リーダーのきほん100」が紹介されています。1つの話は1~2分程度で読める内容になっているので、読みたいところからさっと読むことができます。
松浦氏は「はたらくきほん」の1つとして「大変な時こそ力を抜く。」と述べています。この話の中の「そんな大変な時こそ、一旦冷静になって、力を抜くことを心がけましょう。ふっと力を抜くと、気持ちの上でも、頭の中にも、余白ができて、今どうするべきかがよくわかるものです。何か起きたら、まずは、肩の力を抜いて、リラックスすることが先決です」といった言葉からは、松浦氏が今まで直面した困難な事態を乗り越えてきたときの仕事に対する姿勢を感じることができます。
未だかつて経験したことのない大変な状況ではありますが、仕事のやり方が大きく変化したり家で過ごす時間が増えたりしている今、この本を通して「しごとのきほん」を振り返ってはいかがでしょうか。仕事に悩んだ時、行き詰まった時、読者の背中をそっと押してくれる言葉がいっぱいつまった一冊です。
公開日:2020年04月15日
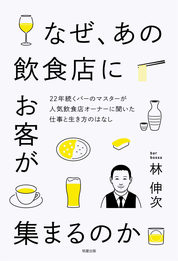 『なぜ、あの飲食店にお客が集まるのか』林 伸次/著 株式会社旭屋書店
『なぜ、あの飲食店にお客が集まるのか』林 伸次/著 株式会社旭屋書店
この本は、22年続く老舗ワインバー「bar bossa(バールボッサ)」の店主である著者が、同業者ならではの視点で、「なぜ、あの飲食店にお客が集まるのか」をテーマに、東京の気になる人気飲食店の店主にインタビューし、対談形式で書いています。
ワインバー・カフェ・立ち飲み店・酒場・和食店・多国籍料理店など、様々なジャンル20店の、開業のきっかけから準備、飲食店ならではの経営の話、たとえば物件の家賃や用意したお金、内装の費用、売り上げなどを、一歩踏み込んで聞いています。
20店に共通の成功法則を見出すのではなく、それぞれ違うビジネスモデルとして紹介し、仕事に対する店主の思いや生き方、繁盛する店に導いたストーリーを読者に伝えてくれます。そのキーワードは、行動力、発信力、バランス感覚、個性、人を育てる、可能性の探究、ワン&オンリーのお店などです。
各店主からは「いつか飲食店をやってみたいあなた」にエールを贈る一言があります。著者自身からも、いろんな人との出会いがあり、「飲食店をやるのは大変だけど、楽しい」という、真っすぐなお店に対する愛情が伝わってきます。
この本を読み終えた後、様々なストーリーがある飲食店を訪ねたくなり、また「自分もそんなお店をやってみたい」という気持ちになる一冊です。
公開日:2020年03月19日
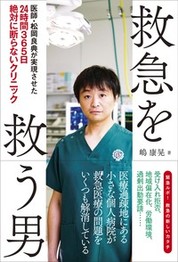 『救急を救う男 医師・松岡良典が実現させた24時間365日絶対に断らないクリニック』嶋 康晃/著 現代書林
『救急を救う男 医師・松岡良典が実現させた24時間365日絶対に断らないクリニック』嶋 康晃/著 現代書林
鹿児島県南九州市の過疎地・川辺町にある「松岡救急クリニック」は、地域のかかりつけ医として外来診療を行いながら急患を受け入れる救急専門の個人病院です。この本は個人で救急クリニックを開業した松岡医師の生きざまと、救急医療の一つの理想形を紹介しています。
ニュースで救急車が病院に受け入れてもらえず、たらい回しされるということを耳にしたことがあるのではないでしょうか。また、救急病院というと、大学病院や総合病院などの大・中規模の病院をイメージするのではないかと思います。
しかし、松岡医師は「近所のコンビニエンスストアのような使い勝手の良い救急クリニック」を目指し、「24時間365日患者を絶対に断らない」というポリシーのもと救急医として、地域に医療を提供しています。患者が困っていることを解決する・病気を治すということを一番に考えながらも、医療従事者の自己犠牲で成り立つのではなく、やりがい・休日・給与のワークライフバランスを重視しています。また、分院として同じ運営ノウハウによる救急クリニックを、全国の医療過疎地や医療僻地に広げる試みも進めています。
自分にしかできない新しい救急医療の形をつくるという思いがあるとはいえ、なぜ個人でこのようなクリニックを開業できたのか、日本の救急医療の問題はどのようなものなのかを松岡医師の姿から知ることができる一冊です。
公開日:2020年02月18日
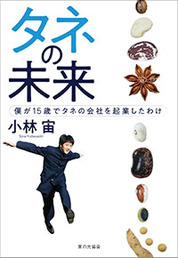 『タネの未来 僕が15歳でタネの会社を起業したわけ』小林 宙/著 家の光協会
『タネの未来 僕が15歳でタネの会社を起業したわけ』小林 宙/著 家の光協会
タネがいつか消えてしまうかもしれないと、考えたことはありますか?
著者は、小林宙(そら)という高校生です。この本には、タネの話、小林さんがタネの流通・販売を手掛ける会社を起業したきっかけやその事業の内容について書かれています。
今、「国内の優良品種が海外へ流出するのを防ぐため」という理由で、農家が自分で育てた作物からタネをとることについて、制限を強めようとする動きがあるそうです。小林さんは、遺伝子組み換え作物が普及したときのことを想定しているのではないかと考えています。
遺伝子組み換え品種のタネは、F1品種(雑種第一代品種)のタネと違い、二代目のタネも一代目の性質を失わず、他のタネと見分けがつきません。そのため、在来種を育ててきた農家が「うちの遺伝子組み換え品種との交配種を育てるのは権利の侵害だ」と企業から訴えられる事例が、世界でいくつも起きており、企業側が裁判で勝つこともあります。
こうして、在来種が駆逐される恐れがあり、日本や世界にもともとあったタネは、数が減っていくことが予想されています。
そこで小林さんは、めずらしい伝統野菜のタネ・消滅する可能性の高いタネを、全国から集めて販売する事業を立ち上げました。ごく小さな地域に留まり、なくなりそうなタネの数々を取り寄せて、流通させることで保存していくことを目指しています。
タネの未来を深く考えて行動する姿に、胸が熱くなります。タネの重要性や置かれた現状について知り、誰かに伝えたくなります。
公開日:2020年01月17日
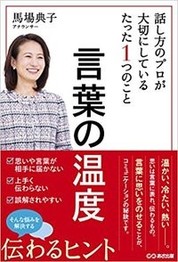 『言葉の温度 話し方のプロが大切にしているたった1つのこと』馬場 典子/著 あさ出版
『言葉の温度 話し方のプロが大切にしているたった1つのこと』馬場 典子/著 あさ出版
著者はフリーアナウンサーとして活躍している馬場典子さんです。
馬場さんは、本書の中で「『温かい言葉に救われた』『冷たい言葉に傷ついた』というように、言葉には"温度"があります」、「言葉の温度は、心を素(もと)にしながら、声のトーンや大きさ・話し方や聞き方・言葉遣い・ニュアンス・間・表情など、コミュニケーションの"総合力"なのです。」といわれています。
本書には、アナウンサーとしての経験に基づいた「伝わる」コミュニケーションのノウハウが満載です。声の出し方、話し方や言葉遣い、話の聞き方、言葉を伝えるときの心構えなどを磨く方法が、「心」「技」「体」に分けて紹介されています。また「初対面の印象をよくしたい」「プレゼンに臨むとき」などのシチュエーション別の伝え方のコツもあります。
本書のPart2「『体』伝わる声を身につけよう」で紹介されている、喉に負担をかけずに奥行きと張りのある声を出す腹式呼吸のやり方や、発音を明瞭にする口・舌・顔の筋肉をほぐすエクササイズは、誰でもすぐに実践できそうです。
「アナウンスメント技術は専門的なスキルと思われるかもしれませんが、決して特別なものではありません。むしろコミュニケーションの基本が詰まっている」と伝えています。
仕事では、上司や同僚や部下、仕事の取引先など様々な相手とのコミュニケーションが必要です。
この本を読んで"言葉の温度"は話し手の"心そのもの"と著者がいうように、自分の思いや言葉が相手に「伝わる」コミュニケーションを実践してみませんか。
公開日:2019年12月28日
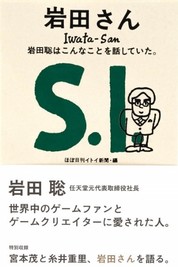 『岩田さん 岩田聡はこんなことを話していた。』岩田 聡/(述) ほぼ日刊イトイ新聞/編 ほぼ日
『岩田さん 岩田聡はこんなことを話していた。』岩田 聡/(述) ほぼ日刊イトイ新聞/編 ほぼ日
「岩田さん」とは、ニンテンドーDS、Wiiといった革新的なハードをプロデュースした任天堂の元代表取締役社長の「岩田聡」(いわた さとる)さん。学生時代からアルバイトをしていたゲーム制作システムの開発などを行うHAL研究所に就職、開発者として数々のゲームを世に送り出し、33歳で社長に就任します。15億円の借金を抱えた状況からのスタートで、会社を立て直した後に、任天堂に入ります。
この本は、ウェブサイト「ほぼ日刊イトイ新聞」に掲載された「岩田さん」のインタビューや対談などから抜粋したことばを、ひとり語りのかたちで再構成しています。まるで「岩田さん」が直接話しかけてくれているような気持ちで読み進めることができます。
「判断とは、情報を集めて分析して、優先度をつけることだ。」ということばは、HAL研究所の社長時代、会社が経営危機に陥っていたとき、社員ひとりひとりと面談を行ったなかで見つけたことでした。
「考えようによっては、仕事って、おもしろくないことだらけなんですけど、おもしろさを見つけるおもしろさに目覚めると、ほとんどなんでもおもしろいんです。」
「人がよろこんでくれる、というゴールさえあれば、どれだけ難しい問題であっても、当事者として取り組み、解決策を考えてしまう。」
などのことばからは、「岩田さん」の多彩なビジネスの経験からつくられた経営理念、価値観、哲学はもちろん、誠実であたたかい人柄まで伝わってきます。
「岩田さん」は、2015年7月、55歳で亡くなられます。
岩田さん自身は、生前は求められても著書を出す意思はなかったそうですが、深い縁があった糸井重里さんが、現在、そして未来に「岩田さん」のことばを残したい、と本にまとめたとのこと。読者それぞれの仕事や人生に響くことばがきっと見つかると思います。