公開日:2025年09月10日
 『グラレコの基本』本園 大介/著 日本実業出版社
『グラレコの基本』本園 大介/著 日本実業出版社
絵で物事をリアルタイムに記録するグラレコ=「グラフィックレコーディング(Graphic Recording)」をご存知ですか。講演や会議の内容をまとめて参加者に伝えるための手法です。
著者はグラレコの魅力を「話を聞いて、言葉や文字では見えづらいものを可視化・整理することによって、物事の本質への理解が深まり、対話できること」だと言います。また、絵を上手に描くことよりも分かりやすく描くことが大事だと言い、グラレコをコミュニケーションのきっかけにすればいいとも言います。
グラレコを始めるために必要なものはペンと紙、そして「描く」を楽しむ気持ちです。
本書では、絵が得意でない人でもグラレコが描けるようになるために、まずChapter2で「○・△・□」の3つの基本図形を用いたモノの描き方、人を○と線だけで描く方法などを紹介しています。
Chapter3ではグラレコを描く基本的な流れ「聞く(聴く)=インプット」→まとめる(要約・解釈)→「描く=アウトプット」について紹介しています。
このグラレコを実践することで、絵を描く力、話をまとめる力、プレゼンの力を得ることができ、ビジネスに活かせる能力が身につくとのことです。
絵を描くことが苦手な人はまずはスケジュール帳やカレンダーに、絵を描くことは好きだけどコミュニケショーンが苦手な人は対話のきっかけを作るために、グラレコを活用してみませんか。
公開日:2025年08月10日
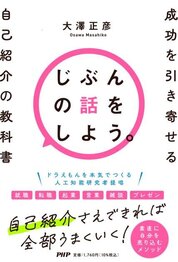 『じぶんの話をしよう。』大澤 正彦/著 PHP研究所
『じぶんの話をしよう。』大澤 正彦/著 PHP研究所
「じぶんの話」それは自己紹介のこと。この本は、著者が日頃から実践している自己紹介の方法や、自己紹介をすることで得られる効果について書かれています。
著者の大澤氏は、人工知能を専門に大学で教鞭をとる研究者です。幼少の頃からの夢は「ドラえもんをつくること」。夢の実現に向け、仲間を増やすために取り組んだ戦略的な自己紹介でオンリーワンの存在になった経験から、学生達に「自己紹介」の講義もしています。
著者は、本書のなかで「自己紹介を通して自分に向き合うようになると、自分のやりたいことや、得意不得意、好き嫌いなど「自分のこと」がよく理解できるようになる」「自己紹介を通して自己理解が進むと、チャンスが巡ってきたときに、チャンスを逃さなくなる」と述べています。
序章では人工知能の研究者が大学で自己紹介を教える理由について、第1章では自己紹介すると夢が叶うのはなぜかというテーマで、第2章では「自己紹介とは○○である」と題し、「自己紹介とは、商品紹介である」「自己紹介とは、物語である」など様々に定義づけしながら自己紹介の詳細について伝えています。第3章の「戦略的な自己紹介のつくり方」では、自己紹介の3要素として①ターゲット②目的(ターゲットにとってほしいアクション)③シチュエーションを挙げ、その中で自己紹介のシチュエーションは、初対面の時に限らず「上司に自分のことを引っ張り上げてほしい」「次の案件を自分に任せてほしい」など、要望を叶えたいときも自己紹介の絶好の機会だと述べています。第4章では自己紹介をするための準備と実践方法について具体的に紹介しています。
本の最後で著者は、自己紹介がうまくなる方法は一つ、自己紹介を楽しみ実践することとだと伝え、まずはSNSで発信することを提案しています。さあ、あなたも「#じぶんの話をしよう」を手はじめに自己紹介を練習し、チャンスを引き寄せてみませんか。
公開日:2025年07月10日
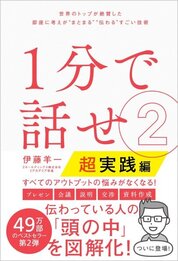 『1分で話せ 2 超実践編』伊藤 羊一/著 SBクリエイティブ
『1分で話せ 2 超実践編』伊藤 羊一/著 SBクリエイティブ
前作の『1分で話せ』は、著者が持っているプレゼンに関する知見が盛り込まれた本でした。今回は、その知見を話す、聞く、資料を作るといった様々な場面で生かしてもらおうとする内容です。
著者は、前作でも紹介されていたピラミッドを使って論旨を整理することを勧めています。ピラミッドは、頂点に「結論」、2段目に3つの「根拠」、3段目に根拠それぞれの「具体例」から成り立っています。この方法で頭の中が整理でき、ロジカルに話すことが苦手な人でも、最低限これに沿って整理して話をすれば伝わると言います。また、人の話を聞くときも、相手の考えをピラミッドに当てはめるように確認していくと理解しやすいのだそうです。
ピラミッドの特徴は、結論が先に示されていることです。その特徴が役立つ場面として、すぐに結論を出さなければならないときのアドバイスをしています。何が一番大事なのかという自分の軸をもとに仮置きの結論を出し議論のたたき台とすることが大事だと述べています。
この他に、頭の中のピラミッドを基本に、説得、交渉、議論などの場面で相手に「伝える」ための実践方法を、事例を挙げながらわかりやすく解説しています。
本書は、話すことに関わらず、伝えるということ、もっと言えばコミュニケーションをいかに円滑に行えるかのヒントが詰まっています。前作を読まれていない方にもお薦めの本です。
公開日:2025年06月10日
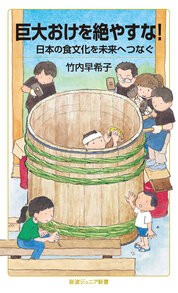 『巨大おけを絶やすな!』竹内 早希子/著 岩波書店
『巨大おけを絶やすな!』竹内 早希子/著 岩波書店
歴史の流れの中で、失われていく仕事があります。巨大な「桶」を作ることもその一つでした。途絶えかけた技術をビジネスチャンスととらえ、仕事に込められた文化や心をも未来に伝えようと奮闘する、職人たちを紹介します。
小豆島で代々醤油蔵を営む山本さんは、ある日醤油を仕込んだ大きな木桶の前で違和感を覚えました。急いで確認すると、中身が大量にもれています。先祖から受け継ぎ、150年もの間使い続けてきた巨大な木桶が、壊れてしまったのです。
その時点で、大きな木桶を作る技術を持ったメーカーは、日本でただ1軒でした。
山本さんはメーカーの職人と話す中で、木桶を作ることや、木桶で仕込む意味を考えさせられます。木桶作りの背景には、材料となる木や竹を育て、自然とつながって生きる文化があります。また、木材を緻密に削り、組み合わせ、長い竹を編んだたがで締めて大桶を作る技術は、日本独特のものです。直径2.3メートル、高さ2.3メートル、約5,400リットルもの量を仕込むことができる桶。時を重ねる中で、桶や蔵にすむたくさんの菌が働き、醤油や味噌、酒などの伝統的な食品を、独自の味や香りに熟成させていくのです。
山本さんは、木桶作りの技術をなくしてはならないと、自分たちで受け継ぐ決意をします。「木桶職人復活プロジェクト」を立ち上げ、「困難」を「おもろい」に変えていくパワーが、熱く伝わる一冊です。
公開日:2025年05月10日
 『聴きポジのススメ』堀井 美香/著 徳間書店
『聴きポジのススメ』堀井 美香/著 徳間書店
著者の堀井氏は、局のアナウンサー時代に様々な番組を担当するなかで、司会やインタビュアーなどコミュニケーションを必要とする仕事に多く携わり、その経験を通じ「聴く力」を培ってきました。著者は、会話には「話し手のポジション」と「聴き手のポジション」(略して「聴きポジ」)があり、意識して「聴きポジ」に立つことで会話そのものを楽しんだり、会話の主導権を握ったりすることができると言います。
本書では、読者が「聴きポジ」を実践できるよう、第1章では「小手先の聴き上手では幸せな会話はできない」、「聴きポジに徹するのは意外と難しい」など、「聴きポジ」に立つための心構えを、第2章、第3章では「聴く」テクニックや仕事での活かし方を紹介しています。会話をする前の下調べも聴く力の一つで、クライアントとの良好な関係を保つために業界新聞や相手企業の過去のニュースを「日経テレコン」で調べることを勧めています。(ちなみに、「日経テレコン」は、中央図書館で調べることができますよ。)
第4章、第5章では、「よりよく聴く」ために不可欠な、相手が話しやすいと感じる声の磨き方や話し方も紹介しています。声を育てるトレーニングは、イラスト付きで分かりやすく、すぐにでも試してみたくなります。
営業や顧客対応などの場面で、会話や雑談を苦手に感じる方、「聴きポジ」を実践し、ビジネスに活かしてみませんか。
公開日:2025年04月11日
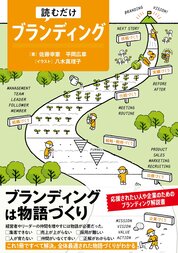 『読むだけブランディング』佐藤 幸憲、平岡 広章/著 白夜書房
『読むだけブランディング』佐藤 幸憲、平岡 広章/著 白夜書房
起業したものの、多くの問題に振り回されていませんか?
著者自身、起業後に様々な問題を経験するうちに、問題解決をするには企業全体のブランディングが必要だという結論にたどり着きました。ブランディングとは、企業の物語を紡ぎ、消費者や関係者に伝えていく活動です。ブランディングをしていくと、取り組むことが明確になり、生産性が上がる。さらに仲間が増え、応援されるようになります。
本書はブランディングを学ぶ人に分かりやすいよう、その工程を農業に例えています。農業においてまず土壌を育てるように、企業の原点から見つめ直し整えることからスタートします。次に収穫量を決める(目標設定)、そして種を植える(戦略・戦術作り)と、7章にわたって解説しています。
各章末には、図やイラストを用い考え方のポイントが視覚的に分かりやすくまとめられていて、最初に図やイラストのページを読んで本章の解説に立ち返るという読み方もできます。
著者は、組織全体が小さいことでスピード感を持って一から取り組むことができる中小零細企業こそ、ブランディングを進めるべきだと言います。何の特徴もない会社を変えたいと思っていたら、この本でブランディングを学んでみませんか。
公開日:2025年03月11日
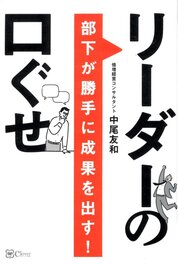 『部下が勝手に成果を出す!リーダーの口ぐせ』中尾 友和/著 Clover出版
『部下が勝手に成果を出す!リーダーの口ぐせ』中尾 友和/著 Clover出版
月締めの報告を見て、業績の数字が伸び悩んでいると感じているリーダーの方もいらっしゃると思います。チームのメンバーにもっと活躍してもらうために、「口ぐせ」を使ってみてはいかがでしょうか。
本書の特徴の一つは、チームの稼ぐ力を倍増させる口ぐせがダイアリーになっていることです。毎月の締め切りを終えた26日からスタートして、翌月の目標設定やその達成に向けた行動に効果的な口ぐせを一日ごとに紹介しています。
例えば、営業のやり方がわからないと悩んでいるメンバーには「とりあえず、〇〇してみる?」と声をかけることを勧めています。
まず簡単にできることから着手し、最初の易しいプロセスがクリアできたら次のプロセスへ。「そうやればできるんだ」と一歩を踏み出せたら、あとはその都度報告を聞き、伴走してあげればいいと著者は述べています。
こうした口ぐせを使うことで、リーダーの能力を高めようとしているのが、本書のもう一つの特徴です。
「数字で考えてる?」
「どんな条件だったらできた?」
口ぐせを使って、成果を出して稼ぐ力を磨いていきましょう。
公開日:2025年02月13日
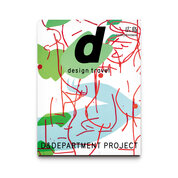 『d design travel HIROSHIMA』D&DEPARTMENT PROJECT
『d design travel HIROSHIMA』D&DEPARTMENT PROJECT
この本は、47都道府県のそれぞれの土地に根付く「個性」や「らしさ」を、「デザイン目線」で取材・編集した旅行ガイドブックの34作目にあたる「広島号」です。本の発行者D&DEPARTMENT PROJECTは、「ロングライフデザイン」をテーマに様々な活動をしています。
本の編集にあたっては、地元の人々とワークショップで意見交換し、本に取り上げた場所や人とは発刊後も継続的に交流を持つという覚悟で、取材先を厳選。編集長自らも広島に来て約2カ月暮らし、県内各地に足を運んで現地の人とコミュニケーションを取りながら取材しています。
平和記念公園や厳島神社など観光で訪れるような場所やお好み焼き店・カフェ、ショップ、宿泊施設などの紹介があるほか、ものづくりにもスポットをあてています。一例をあげると、一生ものの家具を楽しめるマルニ木工、長く売れ続けていてデザイン性も高い無水鍋をつくる広島アルミニウム工業、様々なデニム生地を生みだす篠原テキスタイルなどがあり、地元に根付く技術や人を知ることができます。そのほか、エッセイなどもあり、どのページも読み応えがあります。
広島県を誇りに思うとともに、自分の住む場所で何かを始めたい人にヒントを与えてくれる一冊です。
公開日:2025年01月10日
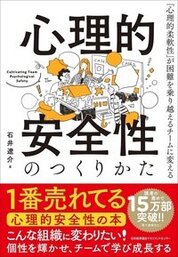 『心理的安全性のつくりかた』石井 遼介/著 日本能率協会マネジメントセンター
『心理的安全性のつくりかた』石井 遼介/著 日本能率協会マネジメントセンター
皆さんは、同僚や先輩、上司と率直に意見を交わしたり、分からないことを気軽に質問したりできていますか?
本書がテーマとしている「心理的安全性」とは、組織やチーム全体の成果に向けた、率直な意見や素朴な質問、違和感に対する指摘がいつでも誰もが気兼ねなく言えることです。この概念は、1999年にハーバード大学のエイミー・C・エドモンドソン教授が提唱し、2012年にGoogleが立ち上げたプロジェクトの調査・分析において、心理的安全なチームはメンバーの離職率が低く、収益性が高いと結論付けたことから、「心理的安全性」という知見がビジネスの世界に広まりました。
著者は、チームの一人一人が素直に意見を言い質問をしても安全だと感じられる状況をつくることは実は難しいが、効果的な組織やチームを作るためには重要な仕事だと述べています。本書では、その仕事の実践に向け、他者への影響力を持つリーダーシップとしての「心理的柔軟性」と、メンバーの行動を変えるために必要な理論・体系である「行動分析」「言語行動」について詳しく伝えるほか、「心理的安全性導入アイデア集」では読者が率先して行動を変えるために役立つアイデアを紹介しています。
役職や立場に関わらず、所属するチームや組織をより良い方向へ変革したいと考えている方に活用していただきたい本です。
公開日:2024年12月10日
失敗したとき、皆さんはどうしていますか?
本書は、LINE公式アカウントの運用プロデュースで成功を収めた著者が、自身の経験から失敗を失敗のまま終わらせずに、リカバリーする方法を説いた本です。
著者は、高校でも、就活でも、就職先でも、その後始めた物販ビジネスでも失敗...。著者曰く、「すべての夢をかなえることができない」人だったそうです。
人生において何をするにも必ず壁に当たってきた著者が、成功できたのはなぜなのか。
それは、ひとつずつ自分なりの解決策や手段を見つけて乗り越えてきたからなのです。失敗を分析することで「失敗をしない戦略」を編み出すことができるから、「失敗はすべて資産」だと著者は伝えます。
「人間関係」で失敗したときや「メンタル」が弱ったときなど、様々な場面での失敗とそれに対するリカバリー術を具体的に挙げており、失敗して何かに救いを求めている人、仕事での失敗を回避したい人におすすめです。
プライベートで先が見えなくなったときなど、仕事以外のことにもヒントをもらえる一冊です。